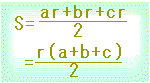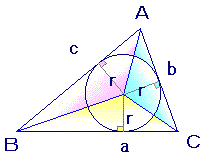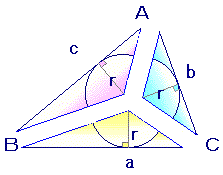|
このページのマイナーチェンジありカバー版ページ
(グーグルブロガー版)は,こちら⇒ ■三角形の内接円の半径の大きさは,面積と関係付けることができます.
■三角形の面積は,いろんな求め方があります.そこで,ヘロンの公式などを用いて三角形の面積を求めておくと,内接円の半径が求まります.
【ヘロンの公式】
三辺の長さがa , b , cである三角形の面積Sを求めるには まず、s= を求めておき 次に、S= …(1) とします。 (1)はS= …(2) と書くこともできますが、教科書では通常(1)の形で書かれています。 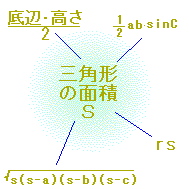 ヘロンの公式で求めた面積は、他の方法で求めた面積と等しいはずだということを使います。 ヘロンの公式で求めた面積は、他の方法で求めた面積と等しいはずだということを使います。三角形の3辺の長さが,それぞれ13,14,15のとき,内接円の半径を求めなさい. (答案) s=(13+14+15)/2=21 ヘロンの公式により、S= 《問題1》 |